
最近、ブラッシング気持ちよくなってきたにゃ。

そう?いっぱい観察してやり方考えたからかなぁ
猫との暮らしの中で「ブラッシング、これで合ってるのかな…?」と不安に思ったことはありませんか?
私たちも同じように悩みました。
特に我が家のうには長毛猫。
毛玉や抜け毛の対策として、できるだけ毎日ケアをしたほうがいいことはわかっていました。
それでも、最初は何から始めたらいいのか手探りでした。
「嫌がられたらどうしよう」「強くやりすぎてない?」そんな不安を感じながらも、少しずつ慣れていきました!
猫の気持ちに寄り添った工夫を知れば、初心者でもブラッシングは無理なく続けられるようにななるはずです!
この記事では、うにとの実体験をベースに、
- ブラッシングの始め方(子猫・成猫それぞれ)
- 嫌がられないための工夫
- 実際の手順とコツ
- ごほうびや習慣化のヒント
などを詳しく紹介します!
ぜひ、あなたと愛猫に合ったブラッシングの形を見つけてくださいね!
猫にブラッシングが欠かせない理由
まずは、うにと暮らしていて「ブラッシングは絶対いる!」と思った理由からお伝えします!
猫はグルーミングをする生き物なので、ある程度は自分で毛並みを整えてくれます。
それでも、(特にうにのような長毛猫の場合は、)それだけでは毛玉になってしまうこともあります。
1歳を超えたあたりから見なくなりましたが、小さい頃はグルーミングがうまくできていませんでした。
そのせいもあってか、よく毛玉ができてしまっていました。
特に、うにに多かったのは、
- 顎下
- 脇下
の毛玉です。
このあたりの毛は背中に比べてパヤパヤでうねりも多く絡まりやすい状態だったのだと思います。
毛玉になると、皮膚を引っ張って痛みの原因になってしまいます。
また、毛玉が大きくなると皮膚病や炎症を引き起こすことも。
さらに、猫はグルーミングの際、抜けた毛を飲み込んでしまいます。
その際、飲み込んだ毛が多ければ多いほど毛玉を吐くリスクが高まってしまいます。
「猫はよく吐く生き物だ」と聞いたこともありますが、吐いている姿を見ると明らかにしんどそうな様子でした。
こまめにブラッシングをして、毛を梳かしたり、抜け毛を取り除いてあげることは、これらのリスクを防ぐ重要なケアであると言えるのではないでしょうか。
短毛猫にもブラッシングは必要か
ここまで、長毛猫で起こりやすいトラブルを紹介しましたが、もちろん短毛猫にもブラッシングは大切なケアになると考えています。
短毛の猫でも、抜け毛はしっかりと発生しますし、皮膚の健康を保つために適度な刺激(血行促進)が効果的だとされています。
ブラッシングによって、
- 抜け毛を取り除いて部屋に舞う毛を減らす
- 日々の健康チェック(部分脱毛や皮膚の異常の早期発見)につなげる
といったメリットもあります。
実際、私たちは毎日のブラッシングのおかげで、うにの顎ニキビも炎症に移る前に発見して対処できました。
無理なく、心地よくケアを続けることで、猫との信頼関係を深めることにもつながると感じています。
ブラッシングはいつから始めるべき?
ブラッシングは、猫を迎えたその日から少しずつ始めるのがおすすめです。
もちろん、生後どれぐらいかによって事情は変わってきます。
とくに長毛猫の場合は、毛玉や抜け毛のトラブルが起きやすいです。
それを防ぐためにも、できるだけ早く小さい頃からケアを習慣にしておきましょう!
子猫の場合
生後3ヶ月未満の子猫は皮膚や被毛がとてもデリケートなため、基本的にブラッシングは不要です。
生後3ヶ月を過ぎ、社会化期に入った頃ぐらいから本格的なブラッシングの練習を始めることをおすすめします。
それでも、いきなり全身をくまなくやる必要はないと思います。
最初は「ブラシを見せるだけ」「触れさせるだけ」からスタートし、少しずつ道具や触れられる感覚に慣らしていきましょう。
ブラッシングが嫌なものにならないように、無理なく自然な流れで少しずつをおすすめします!
成猫の場合
迎えたときにすでに成猫であっても、ブラッシングに慣れていない場合は焦らずにゆっくり始めましょう。
そもそもその場合、スキンシップをとることすら最初はなかなか許してくれない可能性もあります。
- まずは警戒心を解いてもらえるまで待つ
- 触らせてくれるようになるまで待つ
- スキンシップに慣れさせる
- ブラシを見せたり、軽く触れてブラシに慣れさせる
- 少しずつブラッシングをする
一般的には、こんな手順になるのではないでしょうか。
いずれにせよ、子猫の場合も、成猫の場合もいきなり本格的に毛を梳かすのではなく、まずは撫でる感覚でブラシを軽くあてるところから始めることをおすすめします。
猫自身が「ブラシ=嫌なもの」と思わないように、最初は1分、30秒程度でもいいと思います。
少しずつ、成功体験を重ねていきましょう!
体験談:うにはいつから始めた?
うにを迎えたとき、ちょうど生後4ヶ月ほどでした。
私たちは「長毛はできるだけ毎日ブラッシングすべき!」ということを知っていました。
それでも、家に来たその日からブラッシングを始めたわけではありません。
しばらくはサークルの中で過ごさせて、家の環境に慣れてもらうことを優先していました。
そして、家や私たち人間に慣れてくれたかな?と思ったタイミングで、スリッカーブラシを使ってケアを始めました。
とはいえ、最初は手探り状態。
「どれくらいの強さで?」「どのくらいの範囲を?」と迷いながら、うにの様子を見つつ少しずつ続けていきました。
失敗もたくさんありましたが、焦らず、続けてきたから、大きくなった今ブラッシングを受け入れてくれているのだと思っています!
我が家のブラッシングの手順
「ブラッシングをしよう!」となっても、どこから?どのくらい?と迷ってしまうことも多いと思います。
そこで、私たちが普段うににブラッシングをする際に気をつけていることをまとめておきます!
- 始める前にリラックスさせる
- 猫が許してくれるところから始める
- ブラシを強く持ったり押し付けない
ここでは上記の気をつけていることについて、もう少し細かくお伝えします!
まずはリラックスさせることから
まず、ブラッシングは愛猫が落ち着いているタイミングを狙ってするようにしましょう。
食事中や遊んだすぐ後にブラッシングをしようとすると、怒られる可能性が高いです。(うには怒ります。)
また、落ち着いているタイミングであっても、いきなりブラッシングを始めると、警戒モードになることも。
そのため、私たちは、顔まわりや頭を優しくマッサージをすることからスタートしています。
うとうとしてきたり、体の力が抜けてきたのを感じ取れたら、いよいよブラッシング開始の合図です!
ブラッシングは許してくれる部位から
私たちは、うにが撫でられるのが好きな部位(頭、背中など)からいつもブラッシングを始めています。
いきなり苦手な部位(お腹、脇、足など)に触れると、猫パンチや噛みつきなど、明確な拒絶をされてしまいます。
ブラッシングに嫌な印象を持たれると、再びブラッシングを受け入れてもらえるようになるまで時間がかかるかもしれません。
そのため、ブラッシングを受け入れてもらえるようになるためにも、愛猫に「気持ちいい」と感じてもらえるような部位からブラッシングをするように心がけましょう!
ブラシの持ち方と動かし方
完全な経験則になってしまいますが、うにが嫌がりにくかったブラシの持ち方・動かし方も紹介しておきます。
- ペンを持つときのように親指と人差し指で挟み中指をしたから添える
- ブラシの重みだけを利用して、そっと滑らせる
- 毛の流れに沿って撫でる
- 広範囲を一気にやろうとせず、小さい範囲を丁寧に行う
- 毛に強い引っ掛かりを感じたら、無理に引っぱらず、ブラシを軽く浮かせるか、場所を変える


力を入れずに、ブラシを「置く→なでる」くらいの感覚でやると嫌がられにくかったです。
また、小さな範囲を何度も繰り返し梳かすスタイルも、実際に効果的でした。
嫌がる猫への対策
どんなに優しくブラッシングをしていても、猫にも気分があります。
時には嫌がったり、逃げてしまったりすることもあるでしょう。
でも、無理せず、猫の気持ちを尊重しながら少しずつ慣らしていけば、きっと猫にとってブラッシングの時間も心地よいものになっていくはずです!
ここでは、ブラッシングを嫌がる猫への対策を紹介します。
一度に全身のブラッシングは必要ない
- 尻尾を叩きつけるようにブンブン振る
- パンチや蹴りをしてくる
- 噛みついてくる
上記のような行動は、猫からの「もうやめて!」のサインです。
そんなときは無理に続けようとせず、潔く中断しましょう。
今回は背中をメインに、次は腰あたりをメインに、といったように数回に分けて行うのも効果的です。
実際に、うににブラッシングをするときは、「1回で全身をくまなくすること」よりも「少しずつを数回に分けてすること」を大切にしています。
とにかく大切なのは、愛猫にとって「ブラッシングを嫌なものにさせないこと」だと思っています。
猫の気分に合わせて、毎日少しずつケアをしてブラッシングに慣れてもらいましょう!
他のスキンシップも大切
ブラッシングだけを特別な時間にするのではなく、普段から撫でる、触れる、優しく声をかける、といったスキンシップも心がけましょう。
すると、猫も「触れられること」に慣れて、ブラッシングへのハードルがぐっと下がるはずです!
うにの場合も、膝上でくつろいでいるタイミングや、PC作業中に近寄ってきたときなど、自然な流れでブラッシングに移行することで、負担を減らすことができました。
ごほうびを活用する
ブラッシングが終わったあとに、小さなおやつをあげるのも効果的です。
「ブラッシング=いいことがある」と猫が覚えてくれれば、徐々に嫌がることも減っていきます。
ただし、無理に押さえつけながらやった後におやつを与えると逆効果です。
あくまで「猫が落ち着いたまま終われたとき」だけにしましょう。
まとめ:焦らず、少しずつ。猫とのブラッシング時間を楽しもう
ブラッシングは、猫との毎日の暮らしをより快適にするための大切なケアの一つです。
でも、最初から完璧を目指す必要はありません。
まずは、
- いきなりブラシをあてず、マッサージでリラックスさせる
- 猫が好きな場所から、そっと毛流れに沿って撫でるように
- 引っ掛かりを感じたら無理に引っぱらない
- 1回で全身を仕上げようとせず、嫌がったら素直にやめる
この4つを意識するだけで、猫にとっても、飼い主にとっても、ブラッシングはずっとやさしい時間になります。
嫌がる子には、短時間から少しずつ慣らしたり、膝に乗ってきたタイミングを活かしたりと、猫の気持ちを尊重しましょう。
小さな成功体験を積み重ねながら、ブラッシングを「お互いに心地よい時間」に育てていきましょう!
今回の記事がブラッシングでお悩みの飼い主さんと愛猫の助けになれれば幸いです!
以上、うにパパせなとうにママぽなでした!

ふ〜ん。とりあえず気持ちいいなら何でもいいにゃ

ありがと〜。じゃあ脇下いくね〜

シャー!!!

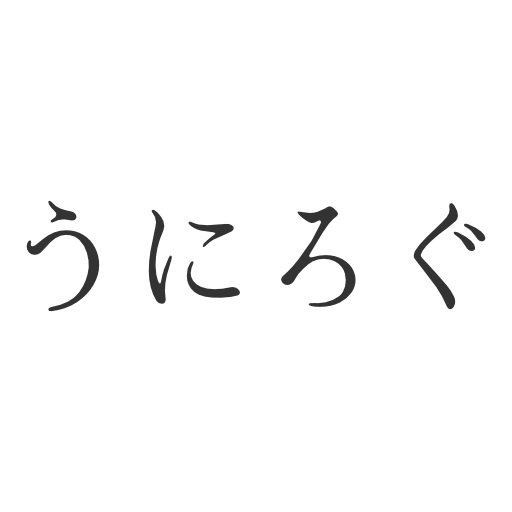

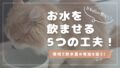
コメント