愛猫『うに』に見つかった先天性の“門脈シャント”。
発症例自体が少なく、当時はその体験談をほとんど見つけられませんでした。
だからこそ、当時の私たちと同じ境遇の方に「少しでも希望になれば…」との思いで、この【門脈シャント闘病記】を残すことにしました。
発作を起こし、一時は体調が大きく崩れる場面もあった『うに』。
それでも、病院スタッフの方々、そして『うに』自身の生命力のおかげで、なんとか危機を乗り越え、無事に退院することができました。
そして、ほっとしたのも束の間に、“退院後のケア”が始まりました。
この【門脈シャント闘病記⑤】では、退院から完治とされるまでを、次の4つ焦点をあててまとめています。
- 後遺症「視力障害」とどう向き合ったか
- 退院後必要になったもの
- 完治までの投薬スケジュール
- 視力回復の経緯
“発作が起きても、後遺症が残っても回復する猫もいる”
このことが、同じ境遇の方にとって、少しでの希望になれば幸いです。
退院直後に始まった“視力障害”への対応
手術・入院を経て、無事退院した『うに』。
「退院したら終わり!」ということはなく、今度は退院後のケアが始まりました。
その中でもまず取り組んだのが、術後発作による後遺症“視力障害”への対応でした。
見えにくい中でも『うに』が安全に過ごせるよう、“環境”や“遊び方”で工夫したことをお伝えします。
退院直後の『うに』の様子
まずは、退院時の『うに』の視力についてのおさらいです。
担当医から“視力障害”について、次のように説明を受けていました。
- 光の調節はできている
- 視覚はおそらく(ほとんど)ない
- 網膜は無事なため、回復する可能性はある
退院時、帰りのタクシーで、『うに』の目の前で指を動かして遊んでみました。
けれども、何の反応も示さなかったので、やっぱり何も見えていなかったんだと思います。
そして、ようやく我が家に帰ってきた『うに』。
見えていないことから、「キャリーから出るのを怖がるかも…」と思いましたが、そんな心配よそに、すぐに久しぶりの我が家を探検しはじめました。]

入院前のように、走り回るようなことはなかったけれど、壁や家具にぶつからないように慎重に歩く『うに』。
髭で空気の流れを感じ取り、鼻や耳の感覚を使ってどこに何があるのかがわかっていたんだと思います。
「自分なら絶対もっと困るのに『うに』はすごいなぁ…」と感動したことを覚えています。
幸い、他には見てわかるような体調の問題はなさそうで、あとは無事に肝臓が育つことを祈るのみでした。
見えなくても過ごせる環境の工夫
壁や物にぶつからなかったとはいえ、『うに』のQOLをあげるため様々な工夫をしました。
その一例が以下の通りです。
- 家具・家電はなるべく壁に寄せる
- 物の配置をなるべく変えない
- 出した物は使わないときは片付けて、歩けるスペースを広げる
- ペットマットを置き足腰の負担を和らげる
- 高所への足場を封鎖する
- フード・水は複数の行きやすい場所に置く
高所の危険には特に注意を払いました。
一度だけ、私たちの不注意で『うに』が高さ40cmほどのベッドに登ってしまったことがあったんです。
このときの『うに』は、飛び降りることを躊躇しているようでした。
そして、助けが間に合わず、飛び降りてしまい『うに』は着地に失敗。
結果、バランスを崩してよろけてしまいました。
このことがあって、なるべく寝室を含め、危険な場所には行けないように道を封鎖。
また、万が一、登ってしまいそうな場所には、着地場所にペットマットを敷くことで対応しました。
以降、完治とされるまで事故が起きることはなく、『うに』の安全を守ることができました!
視力障害でも遊べる工夫
ストレスの発散目的や『うに』に適度な刺激を与えるためにも、遊ぶこともかかしませんでした。
見えていない『うに』でも遊べるように、次のような工夫をしました。
- おもちゃを床に擦るように動かして、音がでるようにする
- 動かし方も“ガシャ…ガシャ…ガシャ…”と間をおいて動かし、捕まえやすいよくする
- ぶつかって怪我をしないように、広いところで遊ぶ
その甲斐もあってか、見えていない状態の『うに』とも十分に遊ぶことができました。
こうした工夫をする中で、『うに』からは、視力に障害があっても、少し工夫をすれば、一緒に暮らすことに何の不自由もないことを学ばせてもらいました。
術後服の調整と管理
門脈シャントの手術に限らず、開腹手術をした猫は“エリザベスカラー”や“術後服”の着用が推奨されています。
これは、傷口をグルーミングして舐め壊さないようにするための処置です。
『うに』も病院から「縫合したところの瘡蓋が取れるまで、術後服を着させること」と指示がでていたので、通販で2着ほど購入しました。
ところが、ここで“術後服のサイズが合わない”という問題が発生。
『うに』の体重や年齢、おおよその体長から、術後服を選んびましたが、着せてみると10秒も経たずに脱がれてしまいました。
これは“短足マンチカン”という体型的な特徴により、服が合わなかったからだと思っています。
裁縫が得意でない私たちは、『うに』の手や舌が届かない背中側をゼムクリップで留め、脱がれないように対策。
これがうまくいき、ようやく一安心。あわや買い直しになるところでした。


薬の投与スケジュールと減薬の過程
術後発作をおこしてしまった『うに』は念の為、退院してからも投薬は続いていました。
とはいえ、いつまでも薬に頼るわけにはいかないということで、少しずつ減薬していきました。
ここでは“薬の種類”や“投与の方法”、“減薬のスケジュール”についてお伝えします。
処方された薬の種類
発作をコントロールするために処方されたのは“フェノバール”という抗けいれん薬でした。
また、フェノバールには胃腸が荒れやすくなるという副作用があったため、それを抑えるために、“エビオス(整腸剤)”も処方されていました。
薬はどちらも粉末状で、混ぜられた状態で薬包紙に入れてもらっていました。
そのため、わざわざ2種類ずつ薬をあげずに済んで、本当に助かりました。
薬のタイミングと投与の方法
『うに』へ投薬は“朝・夕の1日2回”のタイミングでおこなっていました。
最初は病院からもらっていたシリンジに入れて薬を飲ませていたものの、次第に薬包紙を破る音に反応して近寄ってくるように。
そのため入院前と同じように、薬包紙を舐めさせて薬を与えるようになりました。
シリンジでの投与は少し難しさも感じていたので、飼い主としては『うに』にとても助けらたと思っています。
減薬の流れ
投薬生活は9/9に退院してから、10/20までの41日間続きました。
また、9/30に経過観察のため病院へ。
この日の診察で“経過良好”とされた『うに』は、翌日の10/1からめでたく減薬。
1回の投与量が“効果があるとされる用量の半分ほど”にまでなりました。
適量でないのに薬を与えていた理由は、担当医の「徐々に薬を抜いていく」という方針があったからでした。
減薬後の数日間は、発作が起きないかをとても心配しました。
けれど、そんな飼い主の心配をよそに『うに』は何事もなく薬を飲み切ってくれました。
そして、10/20の経過観察によって、ふたたび経過良好と判断された『うに』は、晴れて「門脈シャントは完治」と判断されました。
視力回復の兆し
「門脈シャントが完治した」と判断されるよりも前、『うに』の視覚にも嬉しい変化がありました。
それは退院からおよそ2週間が経ち、『うに』が家での生活にも慣れはじめた頃でした。
『うに』と遊んでいると、音ではなく目でおもちゃを追いかけるような動きを見せたんです。
「これは…」と思った私は色々と試してみることに。
ここではそのときに試した“視覚の確認”と“病院の診断”についてお伝えします。
見えているかも?と思った瞬間
それは退院後およそ2週間が経ったころでした。
いつものようにおもちゃで遊んでいると、「え?!」と思うことが。
『うに』が目の前で動かされたおもちゃに反応して、顔をおもちゃのある方に動かしたんです。
「気のせいか?」とも思い何度か試してみると、何度試してもおもちゃの動く方に顔を動かしていました。
「ヒゲで空気の流れを読んでる?」と思った私は、“動画”で視覚が働いているか確認してみることに。
全画面表示にしたiPadを床に置き、『うに』の反応を確認してみました。
すると、紐を追いかけて猫パンチを披露する姿を披露してくれました。
他にも色々と試した結果、キラキラしているものへの反応が良いことが判明。
もちろん、どんなふうにどれだけ見えているのかは分かりませんでした。
それでも、「絶対に何かは見えている!」と確信し、泣きそうになるぐらい嬉しかったことを覚えています。
診断での視力回復の確認
『うに』の視覚が働いているかを試して1週間後、薬の処方と経過観察のために病院にいました。
このときに、『うに』が目で物を追いかけて、掴もうとしている動画も見てもらうことに。
それを見た担当医からも「何かは見えてる」との言葉をいただきました。
その後、診察台から飛び降り、華麗な着地を披露した『うに』。
それを見て、今度は「しっかり距離感も測れてそう」と言ってもらうこともできました。
そしていただいた総評は次のとおり。
- 何かは見えているが、どこまで見えているのかはわからない
- ここまで見えていたら、日常生活を送る分に困らないだろう
すでに何かは見えていることを確信していましたが、あらためて、担当医からのお墨付きをもらえたことで、さらに安心することができました。
まとめ:門脈シャント闘病中を振り返って
以上、門脈シャント闘病記⑤でした。
門脈シャントが疑われ、完治とされるまでは84日、生まれた時から数えると283日もの闘病生活となりました。
“生きるために必要な食事が、身体を蝕んでいく。しかも、それが生まれた時から。”
“治すためには手術が必要で、手術をしても合併症を起こせば最悪のケースもあり得る。”
“猫の先天性門脈シャント発症率はたった2%。”
こんな状況だったことを知った時は、「なんでうちの子が…」と正直に思ってしまうこともありました。
初めて迎えた子で、「何年一緒にいられるかな?」と思っていただけにショックもかなり大きかったです。
だから、“完治”と言われた時は、本当に嬉しく思いました。
そして、当時を振り返って思う“読者の方にお伝えしたいこと”もあります。
それは大きく次の3つ。
- 決してあきらめないこと
- 詳細な健康診断を受けさせてあげてほしいということ
- 愛猫と飼い主にとって、納得できる選択ができるように、金銭を準備しておくこと
上からの目線になってしまうかもしれませんが、治療にはかなりのお金がかかります。
だから、「今病気になったら?」という視点をもち、普段から少しずつでもその対策はしておいてあげてほしいと思っています。
そして、以上をもちまして【門脈シャント闘病記】は完結です。
あらためて、門脈シャントと戦う猫とその飼い主の方にとって、少しでも希望になれたら嬉しく思います。
そして、病気で苦しむすべての猫が、少しでも多く元気を取り戻せることを心から願っています。
長くなりましたが最後まで読んでくれてありがとうございました。
以上、
愛猫『うに』
パパ『せな』
ママ『ぽな』
からでした!


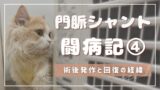
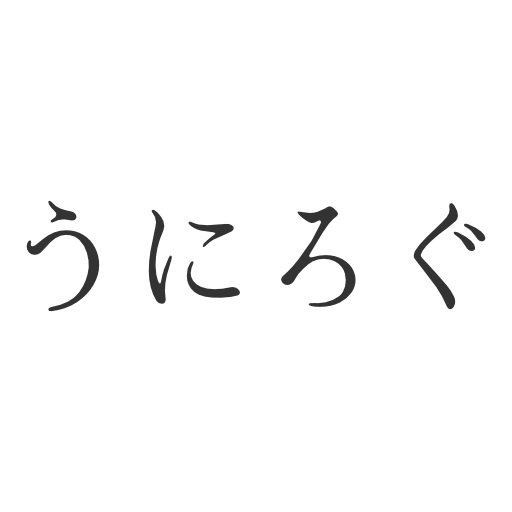
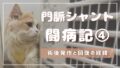

コメント